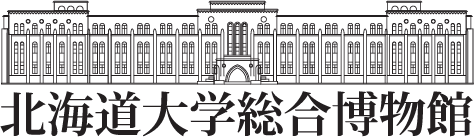【報告】「惑星地球の時空間」展示解説 学生の最終考察
2017年常設展示室新設特別企画「惑星地球の時空間」では、ミュージアムマイスター認定コース「学生参加プロジェクト」の一環として、北大生2名が展示解説に取り組みました。プロジェクトを終えた学生がまとめた最終考察レポートをご紹介します。
展示に込められた全ての意図を来館者に伝えることの難しさを感じるとともに、今回担当した分野を研究しているわけではないが勉強して伝えることができたのはとても良い経験となった。
来館者の展示内容への関心度、観光や学習といった来館目的も様々で、見学の方法もそれぞれで異なる。私は、何か一つでも記憶に残すことができたらと考え、来館者が驚いたり、疑問に思ったりするような解説を心掛けた。そのような解説を心掛けるようになったのは、解説をしていて、来館者の反応や表情を見たり、そのあとの感想や関連した思い出話を聞いたりしたためである。
解説スタッフとして、来館者に展示についての説明を行うと、知識を一方的に伝える・教えることになるかと思っていた。しかし、来館者から知らないことを教えていただいたり、展示物間の関係性を考えるきっかけをもらったりすることで、私自身が学ぶことが多かった。解説者から来館者への一方的な解説ではなく、双方向の関係を築くことができる博物館の場をこれからもっと体験し、様々なことを学んでいきたい。
(理学院自然史科学専攻 博物館教育・映像学研究室 修士1年 徳丸沙耶夏)
「惑星地球の時空間」の展示解説プロジェクトでは、自分から他者へ新たな価値を提供するだけでなく、他者から新たに学ぶことも多かった意味で有意義な時間を過ごすことができたと思う。
キャプションでの解説文が少ない「惑星地球の時空間」の展示室では特に解説スタッフの役割が重要だったのではないだろうか。私は、理学部の地球惑星科学科で地球科学を学んでいることを活かし、多くの来館者が素通りしてしまうような標本であっても、物語があることを伝え、地球の壮大さや科学の面白さを感じてもらうようにするなど、より深い解説をするように心がけた。
また、一方的に話すのではなく、対話をするように意識した。来館者の背景を知ることで、より近い距離で解説することができ、理解を確かめながら対応することができた。さらに、私が知らない地向斜からプレートテクトニクスへの転換期の様子など来館者自身が経験を語ってくださることもあった。
展示解説は、一方向のみになりがちな展示を対話型の二方向にする手段の一つとして有用だと感じ、人と人との結びつきが博物館活動を支えているのだと改めて感じた。
(理学部 地球惑星科学科3年 守屋友一朗)