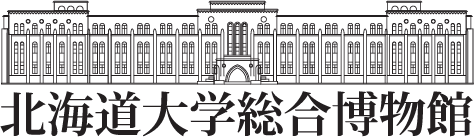授業報告 博物館コミュニケーション特論V 第2回 4月17日
今日の講義では湯浅先生と藤田先生に、博物館での展示解説のお手本を見せて頂いた。受講生が先生の解説を聞きながら、館内を1階から3階までまわるという講義形態で、実際の展示解説のツアーの雰囲気を体験できる講義であった。さらに解説をする際のポイントや展示を制作した時の工夫なども展示解説にまじえて語られ、受講者がこれから自分の展示解説をどのように組み立てていくのか、イメージしやすい内容であった。
先生方の解説は、模型や年表を前にした解説や、標本を用いての解説、解説パネルなどには書かれていない裏話をまじえた解説など、様々な方法をとっており、来館者を飽きさせない工夫があった。また展示においても、スペースの活用も兼ねて収蔵庫も見せてしまう大胆な方法や、来館者からの質問に回答していく掲示板、北大の研究や歴史の特色を生かした展示など、大学の研究と市民の学びをつなぐ様々な工夫があった。
最後に展示解説をするにあたり特に意識すべきことが3点強調された。まず博物館の公式の見解と自分個人の意見をわけること。次に聞いている人の目を見て、一人一人にしっかり伝わるように話すこと。そして裏話などもまじえてここでしか聞けない解説、その人にしか話せない解説を作ることである。
来週からいよいよ、受講者それぞれが自分の展示解説のシナリオづくりに入る。展示解説には様々な工夫の仕方があることが今日の講義で分かり、とてもやりがいを感じている。
(農学院環境資源学専攻 修士1年 宮本柚貴)
アンモナイト展示(ミュージアムマイスターコース学生参加プロジェクトで制作)には、
この授業に参加する安藤さん、木野さん、矢部さんらが関わった
展示室で解説方法について学ぶ宮本さん