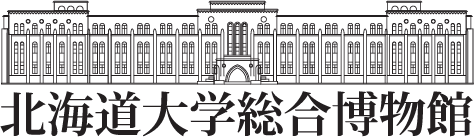【報告:博物館土曜市民セミナー】 2013年12月14日 「食快感の解剖学 : どのようにして食べ物を認識しているのか」 開催
タイトル:
「食快感の解剖学 : どのようにして食べ物を認識しているのか」
講演者:
岩永 敏彦
(北海道大学 大学院医学研究科 教授)
日時:
2013年12月14日(土)13:30-15:00
場所:
北大総合博物館「知の交流」コーナー
概要:
味を感じるために、われわれは舌の表面に味蕾(みらい)をもっている。この構造物は5種類の味、すなわち甘味、塩味、酸味、苦味、うまみを識別できる。しかし、これだけでは複雑な味覚の説明はつかない。辛み、のどごし、温度感覚なども重要な要素であり、これらは口や喉の神経が直接感じているようだ。ビールは喉で味わっているというし、麺食では喉を通過するときの快感が重要である。飲み込んだ後は胃や腸に存在するセンサー細胞がそれらを認識して、効率のよい消化吸収を導く。このセンサー細胞は神経との連絡がないため、興奮しても意識にはのぼらない。われわれは、飲みこんだ後のことまで感知しなくてもよいわけである。
セミナー当日、会場には多くの市民が詰めかけ、岩永 先生の講演に耳を傾けておりました。講演中、時折 ユーモア溢れる話も飛び出し 会場は終始和んでおりました。受講者からの質問も多く寄せられました。

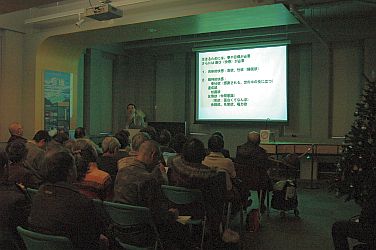
【↑土曜市民セミナーにて講演する 岩永 先生】